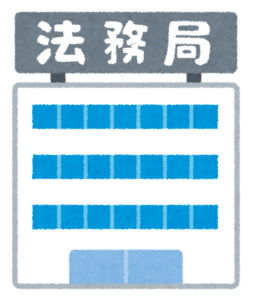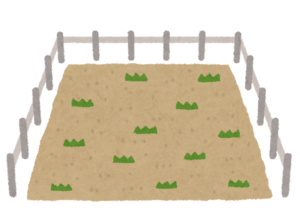留置権に基づく競売の方法
この記事を書いたのは:清水 洋一

1 序論
⑴ 留置権とは,他人の物の占有者がその物に関して生じた債権の弁済を受けるまで,その物を留置して債務者の弁済を間接に強制する担保物権のことです(民法295条1項)。
例えば,自動車修理工が車両を預かって修理・改造を行ったにもかかわらず,所有者が代金を支払われないときに,代金が支払われるまで当該車両を占有し続けることができます。所有者の立場からみれば代金を支払わない限り,車両が手元に戻ってこないため,代金の支払を間接的に強制されるという仕組みです。
⑵ では,留置権者はいつまでその物を留置することができるのでしょうか。答えは,代金が支払われるまでずっと留置することができます。
正確には,被担保債権(修理請求権など)が消滅するまでですが,自ら留置権を放棄しない限り(物を返還しない限り),所有者だけでなく,第三者にも権利を主張することができます。
⑶ しかし,弁済を受けられないといつまでも留置を継続しなければならないと,留置権者の負担が大きくなってしまうので,「留置権に基づく競売」が認められています(民執195条)。
2 競売手続
⑴ 留置権は,他の担保物権とは異なり(先取特権・質権・抵当権等),物の交換価値から優先弁済を受けることはできず,債権の弁済を受けるまで目的物の占有を継続できるという留置的効力しかありません。

つまり,競売により留置物を現金化しても,留置権者は本来,現金を自己のものとすることはできません。
もっとも,留置物の所有者が,被担保債権の債務者である場合,留置権者は,被担保債権と換価金引渡債務を相殺して,事実上の優先弁済を受けることができます。
具体的には,自動車修理工が車両を預かって修理・改造を行って,代金70万円が掛かったとします。所有者が代金を支払わないため競売手続に付して,当該車両が100万円で売却できたとすると,自動車修理工は,①修理代金請求権70万円と②所有者に本来返還すべき換価代金100万円を相殺し,修理代金の優先回収を図ることができます。
そして,差額30万円を所有者へ返還することになります。
⑵ では,競売手続は具体的にどのように申し立てるのでしょうか。
まず,留置権に基づく競売申立は,申立書を提出しなければなりません(民執規1条)。

併せて,留置権者は,競売の申立ての際に留置権の存在を証する確定判決,審判書,公正証書等の謄本を提出しなければなりません。
すなわち,「留置権の存在を公証する書証」が必要です。学説上争いがありますが,実務上,留置権の存在は私文書(契約書や請求書など私人間で作成した文書)による証明では足らないとされています。留置権に基づく競売手続は,留置権の存在を公証する手続がとても重要です。
そして,裁判所は,申立てを相当と認めると競売開始決定をし,以後,①差押→②換価→③配当の順序で手続が進行していきます。
3 結論

以上のとおり,留置権に基づく競売手続の成否は,「留置権の存在を公証する書証」の存否に関わっていると言っても過言ではありません。
単に留置権を取得するだけでなく,競売手続を見据えてどのような方法・順序で,確定判決,審判書,公正証書等を取得するかは専門的な知識・経験が必要となります。
競売手続による債権回収にお悩みの方は,ぜひ一度専門家にご相談ください。

この記事を書いたのは:
清水 洋一